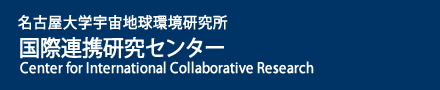終了プロジェクト
IASCプログラム
IASC(国際北極科学委員会)は、北極域の環境研究を包括的に推進するために1990年に設立された非政府の国際科学組織です。IASCは、2018年に改組されたISC(国際学術会議)に属しています。近年、北極域では温暖化による氷床・海氷・永久凍土の融解に代表されるように、自然環境が大きく変化しています。また、北極域の住民生活への影響、北極海航路や天然資源の利用など、人文・社会科学的関心も急速に高まっています。国際連携研究センターに所属する教員(檜山教授)はIASCのTWG(Terrestrial Working Group)のメンバーとなっており、北極海を取り囲む環北極陸域の自然科学と人文・社会科学の環境研究を包括的に推進し、国内外の研究者との連携や連絡調整の一翼を担っています。
北極域研究加速プロジェクト
北極域研究加速プロジェクト(ArCS II:Arctic Challenge for Sustainability II)は、北極域研究推進プロジェクト(ArCS)の後継プロジェクトとして、2020年6月から2025年3月までの約5年弱にわたって実施する、我が国の北極域研究のナショナルフラッグシッププロジェクトです。ArCS IIにおいて、本センターは温暖化状況下における北方林の機能と凍土の動態を調べ、陸域の水循環と物質循環過程を解明することを目的とした研究を行います。そのために、長期の観測実績がある東シベリアの2ヶ所の森林観測拠点を活用し、地上(フラックス)観測データと衛星観測データを最大限に活用することで、北方林の水収支・温室効果気体収支と凍土の相互作用についての統合的な解析を行います。特に、観測拠点における凍土(活動層)の観測を強化し、大気―生態系―積雪―凍土の相互作用の実態把握を推進します。そして、温暖化がもたらす北方林の温室効果気体収支への影響を定量的に解明し、温暖化予測の実装に必要な科学的根拠を提供します。
PAWCs: Pan-Arctic Water-Carbon Cycles
北極域の温暖化は水循環の著しい変動を伴う。温暖化の定量把握と将来予測のためには、北極海の海氷変動を踏まえた上で、大気中の水蒸気の流れ方や降水量(大気水循環)の変動を定量評価するとともに、北極海を取り囲む陸域(環北極陸域)の植生状態・凍土状態・河川流量(陸域水循環)の変動を全て取り扱う研究が必要である。これに加え、環北極陸域における温室効果気体の放出・吸収量 (物質循環)を定量評価する必要もある。温室効果気体の放出・吸収量は環北極 陸域の湛水状態や植生状態によって大きく異なるため、大気-陸域水循環と温室効果気体の動態を統合的に研究することが肝要である。PAWCsプロジェクトは、 北極海氷縮小と永久凍土荒廃を考慮に入れ、過去~現在~将来の大気-陸域水循環の時空間変動を解析し、環北極陸域の植生状態と湛水状態の時空間変動を定量評価する。そして温室効果気体の放出・吸収量の時空間変動を明らかにし、将来予測の不確実性低減に資することを目的とする。
東部ロシア北極・環北極域の凍土水文とレジリエンス
気候変動が東部ロシア北極・環北極域における河川洪水と永久凍土荒廃に及ぼす影響を超学際的に理解することで、地域社会のレジリエンス向上に資する研究成果を創出する。スウェーデンチームは本研究課題全体を総括するとともに、春の解氷と融雪に起因する河川洪水を事前に予報するシステム(河川洪水予報システム)の開発・改良を行い、ロシアチームをサポートすることで、地域社会に河川洪水予報システムを普及させる。ロシアチームはロシア連邦サハ共和国における水文気象観測・河川観測と永久凍土荒廃に関わる調査を行い、地域住民との対話を通して地域社会のレジリエンス向上に取り組む。日本チームは永久凍土荒廃に関わる衛星データ解析を行うとともに、ロシアチームと共同で、永久凍土荒廃と水環境変化に関する超学際調査を行う。また、河川流出モデルの改良によって、北極河川の河川流出に占める融雪水、暖候期降水(降雨)、地下氷融解水(または地下水)の寄与を明らかにする。3ヶ国の間で研究成果を共有し、ステークホルダーミーティングを開催してそれらの知見を地域社会に還元することで、東部ロシア北極・環北極域の環境変化に対する地域社会のレジリエンス向上に貢献する。
ICCONプロジェクト
野辺山電波ヘリオグラフ(NoRH)は、太陽全面を17GHzと34GHzの2周波で同時観測するように設計された太陽観測専用の電波干渉計である。2015年度より、名古屋大学宇宙地球環境研究所が、NoRHの継続運用のために結成された国際コンソーシアム(ICCON)の代表として、運用を行っている。
新学術領域研究 太陽地球圏環境予測(PSTEPプロジェクト)
我々が生きる宇宙「太陽地球圏」の環境は太陽活動に起因して大きく変動しますが、そのメカニズムは未だに十分解明されていません。このため、幅広い宇宙利用と高度な情報化が進んだ現代社会は太陽地球圏の環境変動に対して潜在的なリスクを抱えています。「太陽地球圏環境予測:我々が生きる宇宙の理解とその変動に対応する社会基盤の形成」は、そうした問題の解決を目指して文部科学省科学研究費補助金新学術領域によって組織された全国的な研究プロジェクトです。
SCOSTEP/VarSITIプログラム
VarSITI(Variability of the Sun and Its Terrestrial Impact、太陽活動変動とその地球への影響)は、国際科学会議(ICSU)傘下のSCOSTEP(太陽地球系物理学・科学委員会)が2014年から2018年に推進する太陽地球系科学に関する国際協同研究プログラムです。
SATREPSナミビア(Rice-Mahangu)プロジェクト
アフリカ南部には、洪水や干ばつで食糧不足に陥る地域が多く存在しています。砂漠国のナミビアでも、雨季に出現する季節湿地の不安定な水環境が問題になっており、食糧確保のため現地農業を再構築する必要があります。我々は、洪水や干ばつの年でも常に一定の穀物生産ができるような新農法の考案に挑んでいます。具体的には、新たに導入した作物のイネと現地主食であるトウジンビエを混作し、必要な水の量と経済性を評価しながら新農法を構築します。我々は、混作の適正な組み合わせと配置を探り、経済的な水利用を定量評価するために水文観測を行っています。また、作物の成長が洪水にどの程度依存しているかを調査しつつ、農民の生活向上を促す農法導入と水環境保全の両立を目指しています。季節湿地を最大限に活用した持続可能なモデル農法を南部アフリカに普及させるのが上位目標です。
GEWEX/MAHASRI
モンスーンアジア水文気候研究計画(Monsoon Asian Hydro-Atmosphere Scientific Research and Prediction Initiative : MAHASRI)は世界気候研究計画(WCRP)/全球エネルギー水循環観測計画(GEWEX)/水文気候学パネル(GHP)の地域研究プロジェクトです。